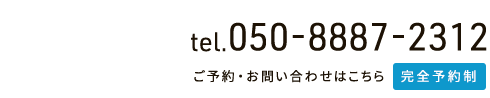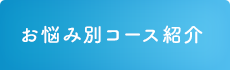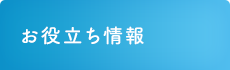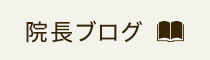整骨院・接骨院の歴史(アジア)
整骨院・接骨院の施術者は、柔道整復師という国家資格所持者たちです。
整骨院・接骨院の歴史は、この柔道整復師についてのお話になります。
名称からも分かるように、柔道整復師の語源は、武道の柔術です。戦国乱世の時代ですが、武道には殺法と活法がありました、その二法を極める人たちを達人と呼ばれていました。
殺法は、言うまでもなく相手を倒す方法で、いわいる武術。
また、活法は、骨折、脱臼など手当て、治療、稽古中に発生した事故などを対処する方法で、発生、発展しました。
時間とともに、殺法はスポーツとして、そして活法は、医療の一部としての柔道整復術として現在に残っています。
1000年も歴史のある柔道整復術
現存しています最古の医学書といわれているもの「医心方」(いしんぼう)には、骨や関節に関する詳細な記述があるといわれています。
そして、平安時代の古い書にも接骨や整骨、接骨博士という言葉が使われています。この時代にはすでに接骨(整骨)という治療の方法が行なわれていたと書かれています。
このことからも柔道整復術の歴史は1000年にも及んでいる事が分かっています。
江戸時代中期には、西洋医学の包帯の使用方法も取り入れられ、江戸時代末期には、漢方医、接骨医などが活躍しました。日本の接骨(整骨)術は隆盛を極めていました。
華岡青洲というと全身麻酔薬の発見と乳がんの手術で有名ですが、一般の医学と平行して接骨術(整骨術)も教えており、整骨・接骨の発展に貢献したひとりといわれています。
法制化するまでの苦難の道筋
医療制度の改革が進められた1874年(明治7年)は、柔道整復術の苦難だったといわれています。
1911年(明治44年)に、鍼灸、あん摩は営業を認められていましたが、接骨術だけが営業を認められていませんでした。
このような背景を受け、1912年(大正元年)から、接骨・整骨術の公認を得る為の運動が高まりはじめました。
1920年(大正9年)、柔道整復師の団体により、内務省令のあん摩術営業取締規制の法制改正で柔道整復師としての身分ができました。
1932年(昭和7年)には日本で初めての、柔道整復師の養成を目的とした学校が誕生しました。
柔道整復術の始まり
昭和に入りますと、戦争や、占領などの圧力や、様々な道のりを経て、1947年(昭和22年)に「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」が公布されることになりました。
1970年(昭和45年)には、「柔道整復師法」が決まりました。
1991年(平成3年)には、学術の部門が始まりました。学術団体としての活動が開始されたときいています。
1993年(平成5年)、柔道整復師は県知事資格から国家資格として認められて、整体、カイロプラティックや他の療術と明確に法律上、区別されました。
この法制化によって民間療法といれていた柔道整復術が代替医療として認知されました。